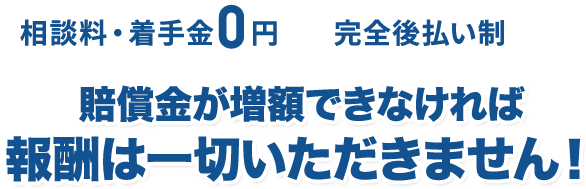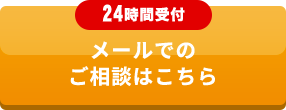交通事故で後遺障害が残った場合の逸失利益の計算方法
交通事故の怪我が完治することなく症状が残ってしまった場合、その後遺障害に対する損害賠償を請求することができます。
障害が残ってしまうことで以前と同じように働くことが難しくなるケースもあるでしょう。
そうした場合、将来得られるはずであった収入を『逸失利益』として請求することができます。
ここでは逸失利益の概要や算定方法について詳しくお伝えします。
目次
後遺障害の「逸失利益」とは
逸失利益は、後遺障害が残ったことによって失われる将来の収入を指します。
例えば、麻痺や痛みによって労働能力が低下すると一定範囲の作業ができなくなったり、重度の後遺障害であれば、全く働くことが出来なくなってしまうことも考えられます。
そのような状態では将来得られるはずだった収入が大幅に減少してしまうことから、損害として加害者に請求することが認められているのです。
逸失利益を請求するには後遺障害等級認定を受けなくてはならない
だたし、逸失利益を請求するには、これまでの診療記録や検査、医師からの症状固定などを経て、後遺障害の認定を受けなければなりません。
後遺障害には1級~14級の等級が設定されていますが、等級によって逸失利益の金額は大きく変わります。
また、適正な等級を受けるためには、障害の度合いを正確に審査機関に伝えなければならない他、それを証明する資料を不備なく提出しなければなりません。
手続きは相手保険会社を通してすることも可能ですが、どのような資料が提出されたか確認することはできません。
検査結果等の提出資料をこちらで選びたい場合には、弁護士等の専門家に依頼し、被害者サイドで手続きを進めたほうが望ましいと考えられます。
後遺障害逸失利益の算定方法で扱う項目について
逸失利益の算定方式は、下記の通りです。
【基礎収入×後遺障害等級に応じた労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】
算定方式について詳しく見ていきましょう。
基礎収入
事故時に就労していた場合、その働いていた収入を基礎収入として考えます。
もし主婦や学生などで就労していない場合は、「賃金センサス」と呼ばれる厚生労働省が発表している賃金構造基本統計調査の結果を当てはめます。
仕事をしていた場合でも、将来高額な収入を得られる可能性があった場合には賃金センサスによって計算することも可能です。
労働能力喪失率
後遺障害の程度には個人差があるのと同様に、労働力の低下率も異なります。
そこで、等級に応じた「労働能力喪失率」を逸失利益の算定で利用することになっています。
等級ごとの労働能力喪失率は以下の通りです。
| 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
|---|---|
| 1級 | 100% |
| 2級 | 100% |
| 3級 | 100% |
| 4級 | 92% |
| 5級 | 79% |
| 6級 | 67% |
| 7級 | 56% |
| 8級 | 45% |
| 9級 | 35% |
| 10級 | 27% |
| 11級 | 20% |
| 12級 | 14% |
| 13級 | 9% |
| 14級 | 5% |
ただし、症状や部位によって労働能力への影響は個人差が見られるため、都度判断されるケースもあります。
労働能力喪失期間
労働能力喪失期間は、後遺障害によって働くことが出来なくなった期間を指します。
基本的には、後遺障害の症状固定と判定された日から67歳までの期間とされます。
子供や学生の場合には18歳からの期間となり、高校生で大学に行く予定出会った場合には22歳からの期間となります。
また、被害者が67歳に近い場合や、既に67歳を超えている場合には、平均余命の1/2の年数を労働能力喪失期間とします。
※障害の程度が軽い場合には労働能力喪失期間が短縮されてしまうケースもあります。
ライプニッツ係数
ライプニッツ係数は、中間利息を控除する計算式です。
逸失利益は、本来であれば毎月毎年給料として得るはずであった収入を、一括で受け取ることになります。
そうすると、被害者は一括で受け取った逸失利益によって財産運用をすれば利益が発生してしまうと考えられます。
この利益は将来得るはずである収入に値しないため、運用利益を差し引くための係数がライプニッツ係数として控除される仕組みになっているのです。
ライプニッツ係数は、就労可能年数に対応する数字が定められているので当てはめて計算します。
まとめ
後遺障害の逸失利益の計算方法を紹介してきましたが、適正な逸失利益を請求するには適正な後遺障害等級が認定される必要があります。
当事務所では、交通事故と後遺障害に詳しい弁護士が等級認定や損害賠償請求など、交通事故に関する問題解決のサポートにあたっています。
後遺障害の知識も豊富だからこそ有利に等級認定されるように進め、最大限のサポートを致します。
越谷市周辺地域のほか、県内や県外の多くの方からご相談をいただいております。
初回相談は無料ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。